中国・清末、京師大学堂の日本人教習・服部宇之吉 ― 2009年02月01日
北京大学の前身・京師大学堂が1901年12月に再開したとき、京師大学堂管学大臣・張百熙は正式に日本駐清国公使・内田康哉に対し、京師大学堂仕学館に日本人法学博士、学士各一名、師範館に文学博士、学士各一名の招聘を要望した。このとき、清国側は日本の著名な法学博士(梅謙次郎、一木喜徳郎、織田萬、岡村司、岡田朝太郎→後に招聘、松崎蔵之助、中村進午等)を指名していたが、当時の文部大臣・菊池大麓は東京、京都両帝国大学長との協議を経て、京都帝国大学教授で法学博士の岩谷孫蔵、東京帝国大学教授で文学博士の服部宇之吉をもって招聘に応じた。
もっとも、岩谷孫蔵は1899年から京都帝大法科教授で独逸法講座を担当していたが、服部宇之吉については東京帝大文科助教授でドイツ留学中だったのを電報で呼び戻し、東京帝大文科教授と文学博士を授与して翌月には清国に送り出したのであった。
京師大学堂の速成仕学館は現在で言えば法学部にあたり、岩谷孫蔵はここに総教習として迎えられた。一方、速成師範館は現在で言えば教育学部にあたり、服部宇之吉はここに正教習として迎えられた。(後に総教習)総教習は学部長にあたり、正教習はその下の教授ということになる。両名の当初の待遇の差から見て、清国側は上記の事情を察していたに違いない。
それでも、服部宇之吉は京師大学堂全教習中で最も高い給料600元(月給)を貰っていたというが、その働きは給料に十分見合うものであった。まず、服部宇之吉が速成師範館で担当していたのは、論理学、心理学、日本語の科目である。北京師範大学の心理学部HPには当時の教科書・服部宇之吉選『心理学講義』(1905年初版、1906年再版発行)の写真が掲載され、師範館時代の心理学の授業について簡単な解説がある。これによれば、心理学は1903年から授業科目となったこと、服部宇之吉が師範館で最初に心理学の授業を行った人物でありこれが中国心理学の最初であったと紹介されている。
また服部は仕学館と師範館より34名の学生を選抜し、専攻を指定した上で日本留学へ送り込んでもいる。このとき服部が日本文部省に格別の配慮を願い出たことで、東京第一高等学校がこれらの留学生教育を担当することとなり、予科が設置されたほどだ。京師大学堂はこの時期、日本を頼りにしており、服部宇之吉を通して、希少な専門書や教具、実験用具、実験薬、新聞雑誌等あらゆるものを日本から購入して急場をしのいだらしい。
服部と岩谷の後も、日本からはさまざまな人材が京師大学堂に投入されたが、これも服部を通じて日本に要請したものであったという。京師大学堂の日本人教員の担当科目は、法律、経済、財政、教育学、文学、数学、物理、化学、動植物学、生理学、心理学、鉱物学、歴史学、論理学、美術、そして日本語等、実に広範にわたる。王暁秋氏によれば、日本人教員は25名であった(「国立北京大学20周年記念冊」所載の京師大学堂教職員名簿による)というが、羽根高廣氏のHP所載のエッセー「北京大学創成期に日本人教授」によれば、1902-1915年の外交文書の記録には29名の名前が残っているそうだ。
その服部宇之吉は5年間の教習生活の後、1909年(明治42年)1月に帰国する。服部宇之吉の帰国に際して、清国政府は日本人教習として最高の二等第二宝星を授与、更に「文科進士」の称号を贈り、「異常出力之才」(傑出した働きをした)と功績をたたえている。
人材、器材、あらゆる面について、日本が服部の要請に応じて京師大学堂に全面協力した背景には、中国への影響力を拡大したいという思惑があった。その思惑の実現のためには、服部宇之吉のように日本文部省にも日本教育界にも通じている人材を送り込む必要があったのであり、また、京師大学堂側にもそのような仲介者が必要だった。服部はその役割を十二分に果たしたといえるだろう。
余談だが、服部宇之吉と繁子夫人は女性教育に対して深い関心を持っており、北京の豫教女学堂の設立に深く関わった。中国の有名な女性革命家・秋瑾を日本留学に送ったのは服部繁子であると言われている。
参考:
江上波夫『東洋学の系譜』(大修館書店、1992)
孫麗青・楊紀国「服部宇之吉和近代中国教育」(幼児網) http://www.lovety.net.cn/html/show-7316.html (中文)
「北京大学創成期に日本人教授」(羽根高廣氏HP) http://www.geocities.jp/hanegao/kiji_24.htm
「心理学院歴史沿革」(北京師範大学心理学院HP)http://www.xinlixuekaoyan.com/html/2006-10/19p2.htm
他
↓応援クリックお願いします(^^)

もっとも、岩谷孫蔵は1899年から京都帝大法科教授で独逸法講座を担当していたが、服部宇之吉については東京帝大文科助教授でドイツ留学中だったのを電報で呼び戻し、東京帝大文科教授と文学博士を授与して翌月には清国に送り出したのであった。
京師大学堂の速成仕学館は現在で言えば法学部にあたり、岩谷孫蔵はここに総教習として迎えられた。一方、速成師範館は現在で言えば教育学部にあたり、服部宇之吉はここに正教習として迎えられた。(後に総教習)総教習は学部長にあたり、正教習はその下の教授ということになる。両名の当初の待遇の差から見て、清国側は上記の事情を察していたに違いない。
それでも、服部宇之吉は京師大学堂全教習中で最も高い給料600元(月給)を貰っていたというが、その働きは給料に十分見合うものであった。まず、服部宇之吉が速成師範館で担当していたのは、論理学、心理学、日本語の科目である。北京師範大学の心理学部HPには当時の教科書・服部宇之吉選『心理学講義』(1905年初版、1906年再版発行)の写真が掲載され、師範館時代の心理学の授業について簡単な解説がある。これによれば、心理学は1903年から授業科目となったこと、服部宇之吉が師範館で最初に心理学の授業を行った人物でありこれが中国心理学の最初であったと紹介されている。
また服部は仕学館と師範館より34名の学生を選抜し、専攻を指定した上で日本留学へ送り込んでもいる。このとき服部が日本文部省に格別の配慮を願い出たことで、東京第一高等学校がこれらの留学生教育を担当することとなり、予科が設置されたほどだ。京師大学堂はこの時期、日本を頼りにしており、服部宇之吉を通して、希少な専門書や教具、実験用具、実験薬、新聞雑誌等あらゆるものを日本から購入して急場をしのいだらしい。
服部と岩谷の後も、日本からはさまざまな人材が京師大学堂に投入されたが、これも服部を通じて日本に要請したものであったという。京師大学堂の日本人教員の担当科目は、法律、経済、財政、教育学、文学、数学、物理、化学、動植物学、生理学、心理学、鉱物学、歴史学、論理学、美術、そして日本語等、実に広範にわたる。王暁秋氏によれば、日本人教員は25名であった(「国立北京大学20周年記念冊」所載の京師大学堂教職員名簿による)というが、羽根高廣氏のHP所載のエッセー「北京大学創成期に日本人教授」によれば、1902-1915年の外交文書の記録には29名の名前が残っているそうだ。
その服部宇之吉は5年間の教習生活の後、1909年(明治42年)1月に帰国する。服部宇之吉の帰国に際して、清国政府は日本人教習として最高の二等第二宝星を授与、更に「文科進士」の称号を贈り、「異常出力之才」(傑出した働きをした)と功績をたたえている。
人材、器材、あらゆる面について、日本が服部の要請に応じて京師大学堂に全面協力した背景には、中国への影響力を拡大したいという思惑があった。その思惑の実現のためには、服部宇之吉のように日本文部省にも日本教育界にも通じている人材を送り込む必要があったのであり、また、京師大学堂側にもそのような仲介者が必要だった。服部はその役割を十二分に果たしたといえるだろう。
余談だが、服部宇之吉と繁子夫人は女性教育に対して深い関心を持っており、北京の豫教女学堂の設立に深く関わった。中国の有名な女性革命家・秋瑾を日本留学に送ったのは服部繁子であると言われている。
参考:
江上波夫『東洋学の系譜』(大修館書店、1992)
孫麗青・楊紀国「服部宇之吉和近代中国教育」(幼児網) http://www.lovety.net.cn/html/show-7316.html (中文)
「北京大学創成期に日本人教授」(羽根高廣氏HP) http://www.geocities.jp/hanegao/kiji_24.htm
「心理学院歴史沿革」(北京師範大学心理学院HP)http://www.xinlixuekaoyan.com/html/2006-10/19p2.htm
他
↓応援クリックお願いします(^^)
京師大学堂教習以前の服部宇之吉 ― 2009年02月03日
東京帝大文科教授と文学博士を授与してまで日本政府が送り出し、清朝政府に「異常出力之才」(傑出した働きをした)とまで讃えられた服部宇之吉の京師大学堂以前について、少し詳しく見てみよう。
服部宇之吉(1867-1939)は福島県出身である。生後一ヶ月にして生後を失い、叔父夫婦に引き取られた。戊辰戦争で実父を失い、逃亡中に負傷した傷が元で左目を失明するなど、幼少時は苦労を重ねたようだ。1872年・明治5年頃に養父が東京で職を得て、家族で東京に移ってからは、麻布小学校に通学、卒業後は私塾に通って漢学、数学、英学を修め、1881年・明治14年に東京開成中学校の前身・共立学校に入学、1883年・明治16年に大学予備門(在学中に第一高等中学校になる)に入学、1887年・明治20年に帝国大学文科大学哲学科に入学した。
1890年・明治23年に東京帝国大学文科大学哲学科を卒業、当時は文学士も法学士と同様に高等文官の資格があったので、役人になるか教員になるか迷っていたときに、東京帝国大学の文科大学長外山正一が文部省専門学務局長・浜尾新に推薦、文部省に入省する。この頃に、文科大学の島田重礼教授に見込まれて、三女・繁子と結婚、媒酌は浜尾新であった。翌年には、役人は合わないと浜尾、外山に申し出て教員に転じ、京都の第三高等学校と東京の高等師範学校で教授となる。しかし、1897年・明治30年に文部大臣となった浜尾新の依頼を受けて秘書官をつとめることになった。その後に文部大臣になったのが、外山正一だったので継続して秘書官を務め、外山の辞任と共に、秘書官を辞したのであった。これは本人が望んだというよりは、上司であり、結婚の媒酌人でもあった浜尾の依頼だけに仕方がなかったのだという。
その後、東京高等師範学校教授と東京帝国大学文科大学助教授を兼任、翌年から東京帝国大学文科大学助教授専任となり、1899年に4年間の清国とドイツ留学を命じられた。このとき、清国に派遣されたのは、東京帝国大学の服部宇之吉と京都帝国大学の狩野直喜である。両名は、義和団の乱に遭い、約二ヶ月の北京篭城を体験することになる。清国からの宣戦布告に伴い、1900年6月19日に24時間以内の退去を通告され、20日から公使館区域への攻撃が始まる。攻撃開始から援軍が到着する8月14日までの約2ヶ月間、の篭城であった。外国人は公使館員とその家族、護衛兵、留学生等を合わせ925名、中国人のキリスト教徒が3000名ほど逃げ込んでいた。護衛兵と義勇軍合わせても481名しかいないという状態、しかも連合国の寄り合い状態で恐怖の2ヵ月を乗り切れたのは、実質的に総指揮をとった日本の柴五郎中佐(数カ国語を解したという)の存在、そして中国人キリスト教徒の存在が大きかったと言うが、なによりも敗戦後の連合国の報復を恐れる清国側の不徹底な抗戦姿勢にあったらしい。
九死に一生を得て無事帰国した服部は、12月にはドイツに向かった。ドイツ留学一年半足らずのときに、文部大臣からの電報で急遽帰国、再び北京へ、京師大学堂へ、今度は教習として赴くことになった。このときの心境は如何ばかりであったろう。
参考:江上波夫『東洋学の系譜』(大修館書店、1992)
柴五郎中佐・服部宇之吉『北京篭城日記』(東洋文庫)
「服部宇之吉」(Wikipedia) http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%8D%E9%83%A8%E5%AE%87%E4%B9%8B%E5%90%89
「義和団の乱」(Wikipedia)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%BE%A9%E5%92%8C%E5%9B%A3%E3%81%AE%E4%B9%B1
↓応援クリックお願いします(^^)

服部宇之吉(1867-1939)は福島県出身である。生後一ヶ月にして生後を失い、叔父夫婦に引き取られた。戊辰戦争で実父を失い、逃亡中に負傷した傷が元で左目を失明するなど、幼少時は苦労を重ねたようだ。1872年・明治5年頃に養父が東京で職を得て、家族で東京に移ってからは、麻布小学校に通学、卒業後は私塾に通って漢学、数学、英学を修め、1881年・明治14年に東京開成中学校の前身・共立学校に入学、1883年・明治16年に大学予備門(在学中に第一高等中学校になる)に入学、1887年・明治20年に帝国大学文科大学哲学科に入学した。
1890年・明治23年に東京帝国大学文科大学哲学科を卒業、当時は文学士も法学士と同様に高等文官の資格があったので、役人になるか教員になるか迷っていたときに、東京帝国大学の文科大学長外山正一が文部省専門学務局長・浜尾新に推薦、文部省に入省する。この頃に、文科大学の島田重礼教授に見込まれて、三女・繁子と結婚、媒酌は浜尾新であった。翌年には、役人は合わないと浜尾、外山に申し出て教員に転じ、京都の第三高等学校と東京の高等師範学校で教授となる。しかし、1897年・明治30年に文部大臣となった浜尾新の依頼を受けて秘書官をつとめることになった。その後に文部大臣になったのが、外山正一だったので継続して秘書官を務め、外山の辞任と共に、秘書官を辞したのであった。これは本人が望んだというよりは、上司であり、結婚の媒酌人でもあった浜尾の依頼だけに仕方がなかったのだという。
その後、東京高等師範学校教授と東京帝国大学文科大学助教授を兼任、翌年から東京帝国大学文科大学助教授専任となり、1899年に4年間の清国とドイツ留学を命じられた。このとき、清国に派遣されたのは、東京帝国大学の服部宇之吉と京都帝国大学の狩野直喜である。両名は、義和団の乱に遭い、約二ヶ月の北京篭城を体験することになる。清国からの宣戦布告に伴い、1900年6月19日に24時間以内の退去を通告され、20日から公使館区域への攻撃が始まる。攻撃開始から援軍が到着する8月14日までの約2ヶ月間、の篭城であった。外国人は公使館員とその家族、護衛兵、留学生等を合わせ925名、中国人のキリスト教徒が3000名ほど逃げ込んでいた。護衛兵と義勇軍合わせても481名しかいないという状態、しかも連合国の寄り合い状態で恐怖の2ヵ月を乗り切れたのは、実質的に総指揮をとった日本の柴五郎中佐(数カ国語を解したという)の存在、そして中国人キリスト教徒の存在が大きかったと言うが、なによりも敗戦後の連合国の報復を恐れる清国側の不徹底な抗戦姿勢にあったらしい。
九死に一生を得て無事帰国した服部は、12月にはドイツに向かった。ドイツ留学一年半足らずのときに、文部大臣からの電報で急遽帰国、再び北京へ、京師大学堂へ、今度は教習として赴くことになった。このときの心境は如何ばかりであったろう。
参考:江上波夫『東洋学の系譜』(大修館書店、1992)
柴五郎中佐・服部宇之吉『北京篭城日記』(東洋文庫)
「服部宇之吉」(Wikipedia) http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%8D%E9%83%A8%E5%AE%87%E4%B9%8B%E5%90%89
「義和団の乱」(Wikipedia)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%BE%A9%E5%92%8C%E5%9B%A3%E3%81%AE%E4%B9%B1
↓応援クリックお願いします(^^)
京師大学堂後の服部宇之吉 ― 2009年02月04日
服部宇之吉は京師大学堂の教習の仕事を終えて帰国後、東大に復帰(1909-、支那哲学講座主任)した。哲学科出身で、ドイツへの留学経験もあり、西洋哲学やその方法論にも詳しかったはずの、服部宇之吉が学術研究のテーマとして選んだのは「礼」の研究であった。(「支那古礼と現代風俗」「井田私考」「宗法考」「礼の思想附実際」など)講義の題目も多くは礼に関するもので、ハーバード大学でも一年間(1915-16年)日本学講座で教授を務めるが、ここでも儒教に関する講義を行っている。
なお、服部宇之吉は九死に一生を得た義和団の乱の賠償金(外務省所管の団匪賠償金)によって運営された中国で行われた東方文化事業、東京に設立された東方文化学院所長(京都にも。こちらは北京篭城で生死を共にした狩野直喜が所長、後の京大人文研)としての仕事にも熱心に取り組んでいる。(東方文化学院は後に東大の東洋文化研究所に吸収合併される)
私見であるが、義和団の乱で二ヶ月間の北京篭城を体験したことが、また京師大学堂の五年間が、服部宇之吉の中の何かを変えたのではないかと思う。中国という不可思議な存在を内側から解明する鍵として「礼」を捉えていたのではないかと想像する。
ところで、服部宇之吉はその後も東大文学部長(1924-1926)、京城帝国大学総長(1926-1928)を兼任、国学院大学総長(昭和4-8)、東方文化学院理事長、同東京研究所長(昭和4-14)になり、また1921年・大正10年からは東宮職御用掛を拝命するなど、順調な出世街道を歩んだ。
ひとつだけ…孫麗青・楊紀国「服部宇之吉和近代中国教育」には、「服部の侵華思想」という見出しもあったのが気になっている。少なくとも京師大学堂時代の仕事にはそのような部分はないと思う。その後のことについては、手元の資料不足でよく分からない。戦前の日本中国学についての何かで見たことがあるような気もする。先行研究がたくさんあるので、もし何か分かれば補足するつもりである。
参考:柴五郎中佐・服部宇之吉『北京篭城日記』(東洋文庫)
孫麗青・楊紀国「服部宇之吉和近代中国教育」(幼児網) http://www.lovety.net.cn/html/show-7316.html (中文)
↓応援クリックお願いします(^^)

なお、服部宇之吉は九死に一生を得た義和団の乱の賠償金(外務省所管の団匪賠償金)によって運営された中国で行われた東方文化事業、東京に設立された東方文化学院所長(京都にも。こちらは北京篭城で生死を共にした狩野直喜が所長、後の京大人文研)としての仕事にも熱心に取り組んでいる。(東方文化学院は後に東大の東洋文化研究所に吸収合併される)
私見であるが、義和団の乱で二ヶ月間の北京篭城を体験したことが、また京師大学堂の五年間が、服部宇之吉の中の何かを変えたのではないかと思う。中国という不可思議な存在を内側から解明する鍵として「礼」を捉えていたのではないかと想像する。
ところで、服部宇之吉はその後も東大文学部長(1924-1926)、京城帝国大学総長(1926-1928)を兼任、国学院大学総長(昭和4-8)、東方文化学院理事長、同東京研究所長(昭和4-14)になり、また1921年・大正10年からは東宮職御用掛を拝命するなど、順調な出世街道を歩んだ。
ひとつだけ…孫麗青・楊紀国「服部宇之吉和近代中国教育」には、「服部の侵華思想」という見出しもあったのが気になっている。少なくとも京師大学堂時代の仕事にはそのような部分はないと思う。その後のことについては、手元の資料不足でよく分からない。戦前の日本中国学についての何かで見たことがあるような気もする。先行研究がたくさんあるので、もし何か分かれば補足するつもりである。
参考:柴五郎中佐・服部宇之吉『北京篭城日記』(東洋文庫)
孫麗青・楊紀国「服部宇之吉和近代中国教育」(幼児網) http://www.lovety.net.cn/html/show-7316.html (中文)
↓応援クリックお願いします(^^)
冬の法隆寺を散策 ― 2009年02月05日

久しぶりの法隆寺。友人4名と共に冬の法隆寺を散策した。観光シーズンではないので、人も少なく、ゆったりと過ごせたのは幸いだった。
境内を巡りながら、この寺が経てきた歴史に思いを馳せた。法隆寺は一度焼失し再建された、と聞いたことがある。聖徳太子による創建は通説では607年、焼失したのは670年(天智9年)のことで、日本書紀に記載されているそうだ。その後、千三百年以上もの歳月、火災や数々の戦乱を逃れてきたのは、本当に奇跡である。無論、その背景には、法隆寺を守ってきた方々の、言い尽くせないほど多くの苦労や努力があったに違いないとも思う。また、仏教文化がインドから中国を経て海を越え日本にたどり着いたというのも、玄奘三蔵のインドへの求道の旅、命をかけて隋や唐に渡って学問を修め、多くの経典や先進の知識文化を携えて帰ってきた僧侶達の存在があってこそである。
最近、般若心経や仏教の歴史、玄奘三蔵の伝記を読んでいる。仏教をもっと知りたいと考えていた矢先の法隆寺行きだったので、私にはこの空間を感じる時間を持てたことは、とてもありがたかった。
今回、朱印帖を初めて購入した。朱印所で書いてもらったのは「以和為貴」、有名な17条憲法の第1条「和を以て貴しと為す」である。これは論語の学而第1「有子曰 礼之用和為貴」から来ている。日付も入れてくれたので、いい記念になりそうだ。
そういえば、見学できなかったが、今日法隆寺では伝統行事・三蔵会が行われた。玄奘三蔵の遺徳を奉賛してその命日に祖師法要を営む、倉時代から江戸時代まで続いていた行事である。明治初年に一旦中断され、昭和58年に再興されたそうだ。
参観の後は門前のお店・松鼓堂で茶がゆをいただいた。はったい粉の香が心地よく、お腹に優しい昼食だった。こうして出かけられたのも友人達のおかげである。女友達と過ごす時間もいいものだ。またの機会を楽しみに。
↓応援クリックお願いします(^^)

境内を巡りながら、この寺が経てきた歴史に思いを馳せた。法隆寺は一度焼失し再建された、と聞いたことがある。聖徳太子による創建は通説では607年、焼失したのは670年(天智9年)のことで、日本書紀に記載されているそうだ。その後、千三百年以上もの歳月、火災や数々の戦乱を逃れてきたのは、本当に奇跡である。無論、その背景には、法隆寺を守ってきた方々の、言い尽くせないほど多くの苦労や努力があったに違いないとも思う。また、仏教文化がインドから中国を経て海を越え日本にたどり着いたというのも、玄奘三蔵のインドへの求道の旅、命をかけて隋や唐に渡って学問を修め、多くの経典や先進の知識文化を携えて帰ってきた僧侶達の存在があってこそである。
最近、般若心経や仏教の歴史、玄奘三蔵の伝記を読んでいる。仏教をもっと知りたいと考えていた矢先の法隆寺行きだったので、私にはこの空間を感じる時間を持てたことは、とてもありがたかった。
今回、朱印帖を初めて購入した。朱印所で書いてもらったのは「以和為貴」、有名な17条憲法の第1条「和を以て貴しと為す」である。これは論語の学而第1「有子曰 礼之用和為貴」から来ている。日付も入れてくれたので、いい記念になりそうだ。
そういえば、見学できなかったが、今日法隆寺では伝統行事・三蔵会が行われた。玄奘三蔵の遺徳を奉賛してその命日に祖師法要を営む、倉時代から江戸時代まで続いていた行事である。明治初年に一旦中断され、昭和58年に再興されたそうだ。
参観の後は門前のお店・松鼓堂で茶がゆをいただいた。はったい粉の香が心地よく、お腹に優しい昼食だった。こうして出かけられたのも友人達のおかげである。女友達と過ごす時間もいいものだ。またの機会を楽しみに。
↓応援クリックお願いします(^^)
中国・清末、京師大学堂仕学館の総教習を務めた岩谷孫蔵 ― 2009年02月08日
少し間があいたが…1902年に服部宇之吉と共に京師大学堂に招かれた京都帝国大学教授で法学博士の岩谷孫蔵についても、詳しく知りたくなり、いろいろ探していた。まず『東洋学の系譜』には載っていなかった。阿部洋『中国の近代教育と明治文化』に詳しいようだが、まだ見ていない。幸いなことに、岩谷孫蔵について言及がある論文・顧祝軒「中国における民事法の継受と[動的システム論]」を見つけたので、この論文の岩谷孫蔵に関する部分の記述を覚え書きとしてまとめておくことにする。
岩谷孫蔵は1867年生まれ、佐賀出身である。東京外国語大学独語科卒業後、1885年より法学研修の為ドイツに留学、イエナ大学、ハレ大学に学んで学位を取得、帰国後は明治法律学校、東京専門学校、第三高等中学教授などを経て、1899年、京都帝国大学法科教授に就任、独逸法講座を担当していた。
1902年、日本は清国側の招聘の要望に応じて人選を行い、法学博士としては岩谷孫蔵が選ばれ、京師大学堂に新設された速成仕学館(現在なら法学部にあたる)の総教習(学部長のようなもの)に就任したのである。担当した学科は「法律学」「経済学」「日本語」であったようだ。
岩谷孫蔵は仕学館創設期の企画、章程の制定、課程の設置などに参加、教学の管理及び、教室、宿舎の建設、教材や参考書の編纂、図書、設備の購入や、時には新入生の選抜試験にも参加したという。
1906年、仕学館は京師法政学堂に改組され、岩谷は引き続き総教習の職に就いた。京師法政学堂は、日本の帝国大学の制度にならって分科大学を開設したものである。実は1906年前後、清政府は将来の立憲政治に備えて、法政の専門知識をもつ官吏を養成する必要があるとして、全国各地方(省)に法政学堂の開設を命じており、1909年11月には全中国の日本人教習の人数は実に500~600名に達していたという。その中でも法政経済関係の教育に従事するものが約50人前後あったそうだ。岩谷の勤める京師法政学堂にも、複数の日本人教習が招聘された。中でも東大教授の岡田朝太郎は総教頭として招聘され、1910年から1915年まで法制科教習を務めている。
京師大学堂速成仕学館から京師法政学堂における岩谷孫蔵の働きは高く評価された。1908年、清朝廷は京師大学堂総監督の要請に応え、服部宇之吉と共に外国人教習としては破格の二等第二宝星を授与している。なお、師範館に招聘された服部以下の日本人教習は1909年に帰国した者が多いようだが、岩谷孫蔵他、京師法政学堂の教習はそのまま残った。
1912年1月1日に中華民国が成立、同年5月に京師大学堂は国立北京大学校となり、厳復が大学校長になる。 岩谷孫蔵は中華民国成立後も引き続き中国に留まった。一時は中華民国総統府の法律顧問となり、その後も法典編纂調査員として仕事を続け、中国初期の会社法である「公司法草案」を民国5年に余?昌(1882-)とともに起草するなど、中華民国初期の法整備に力を尽くし、1917年にはその功労を讃えて二等嘉禾章を授与されている。
結局、岩谷孫蔵は、1902年に北京に赴いて1917年に帰国するまで16年間もの間中国に滞在した。そして1917年に病を患い帰国、翌年の1918年に肺結核で逝去した。
岩谷孫蔵の経歴についての覚え書きは以上である。ところで、この時期、日本人以外にも外国人教習が多く京師大学堂で教鞭をとっていた。そのあたり、新たに分かったことがあれば、補足していくつもりである。
参考:顧祝軒「中国における民事法の継受と[動的システム論]」(2)http://dspace.wul.waseda.ac.jp/dspace/bitstream/2065/2520/1/A03890546-00-078010035.pdf
北京大学法学院 http://www.law.pku.edu.cn/article_one.asp?MID=20038206425342&MenuId=20038206416577&menuname=学院概况
↓応援クリックお願いします(^^)

岩谷孫蔵は1867年生まれ、佐賀出身である。東京外国語大学独語科卒業後、1885年より法学研修の為ドイツに留学、イエナ大学、ハレ大学に学んで学位を取得、帰国後は明治法律学校、東京専門学校、第三高等中学教授などを経て、1899年、京都帝国大学法科教授に就任、独逸法講座を担当していた。
1902年、日本は清国側の招聘の要望に応じて人選を行い、法学博士としては岩谷孫蔵が選ばれ、京師大学堂に新設された速成仕学館(現在なら法学部にあたる)の総教習(学部長のようなもの)に就任したのである。担当した学科は「法律学」「経済学」「日本語」であったようだ。
岩谷孫蔵は仕学館創設期の企画、章程の制定、課程の設置などに参加、教学の管理及び、教室、宿舎の建設、教材や参考書の編纂、図書、設備の購入や、時には新入生の選抜試験にも参加したという。
1906年、仕学館は京師法政学堂に改組され、岩谷は引き続き総教習の職に就いた。京師法政学堂は、日本の帝国大学の制度にならって分科大学を開設したものである。実は1906年前後、清政府は将来の立憲政治に備えて、法政の専門知識をもつ官吏を養成する必要があるとして、全国各地方(省)に法政学堂の開設を命じており、1909年11月には全中国の日本人教習の人数は実に500~600名に達していたという。その中でも法政経済関係の教育に従事するものが約50人前後あったそうだ。岩谷の勤める京師法政学堂にも、複数の日本人教習が招聘された。中でも東大教授の岡田朝太郎は総教頭として招聘され、1910年から1915年まで法制科教習を務めている。
京師大学堂速成仕学館から京師法政学堂における岩谷孫蔵の働きは高く評価された。1908年、清朝廷は京師大学堂総監督の要請に応え、服部宇之吉と共に外国人教習としては破格の二等第二宝星を授与している。なお、師範館に招聘された服部以下の日本人教習は1909年に帰国した者が多いようだが、岩谷孫蔵他、京師法政学堂の教習はそのまま残った。
1912年1月1日に中華民国が成立、同年5月に京師大学堂は国立北京大学校となり、厳復が大学校長になる。 岩谷孫蔵は中華民国成立後も引き続き中国に留まった。一時は中華民国総統府の法律顧問となり、その後も法典編纂調査員として仕事を続け、中国初期の会社法である「公司法草案」を民国5年に余?昌(1882-)とともに起草するなど、中華民国初期の法整備に力を尽くし、1917年にはその功労を讃えて二等嘉禾章を授与されている。
結局、岩谷孫蔵は、1902年に北京に赴いて1917年に帰国するまで16年間もの間中国に滞在した。そして1917年に病を患い帰国、翌年の1918年に肺結核で逝去した。
岩谷孫蔵の経歴についての覚え書きは以上である。ところで、この時期、日本人以外にも外国人教習が多く京師大学堂で教鞭をとっていた。そのあたり、新たに分かったことがあれば、補足していくつもりである。
参考:顧祝軒「中国における民事法の継受と[動的システム論]」(2)http://dspace.wul.waseda.ac.jp/dspace/bitstream/2065/2520/1/A03890546-00-078010035.pdf
北京大学法学院 http://www.law.pku.edu.cn/article_one.asp?MID=20038206425342&MenuId=20038206416577&menuname=学院概况
↓応援クリックお願いします(^^)
「ちょっぴり気まぐれ お月さまのクッキー」 ― 2009年02月10日

昨日は娘の友達のお家に遊びに行った。娘と相談してお菓子を焼いて持っていくことにした。選んだのは「ちょっぴり気まぐれ
お月さまのクッキー」。言うまでもないが、タイトルと可愛らしい形に惹かれたのだ。娘は自分のクッキー、といって喜んでいる。
作り方はシンプル。薄力粉150gとバター(食塩不使用)100g、粉砂糖25gとアーモンドダイス50gを混ぜて、三日月の形にととのえ、170度のオーブンで17分ほど焼いて、熱いうちに粉砂糖をまぶしてできあがり。味見をしたらとっても美味しかった。カロリーは高いけれど、たまにはいいよね?お友達も喜んでくれて大成功(^^)
詳しいレシピは『はじめてさん&ぶきっちょさんのためのお菓子一年生』に。
ちなみに今日は娘が風邪で学校を休んだので、何も出来なかった。娘は、ずっと「おにぎりやさん」をしていて、私はお客さん役…なぜ「おにぎりやさん」なのだろう?
参考:『はじめてさん&ぶきっちょさんのためのお菓子一年生』(主婦の友生活シリーズ、主婦の友社)
↓応援クリックお願いします(^^)

作り方はシンプル。薄力粉150gとバター(食塩不使用)100g、粉砂糖25gとアーモンドダイス50gを混ぜて、三日月の形にととのえ、170度のオーブンで17分ほど焼いて、熱いうちに粉砂糖をまぶしてできあがり。味見をしたらとっても美味しかった。カロリーは高いけれど、たまにはいいよね?お友達も喜んでくれて大成功(^^)
詳しいレシピは『はじめてさん&ぶきっちょさんのためのお菓子一年生』に。
ちなみに今日は娘が風邪で学校を休んだので、何も出来なかった。娘は、ずっと「おにぎりやさん」をしていて、私はお客さん役…なぜ「おにぎりやさん」なのだろう?
参考:『はじめてさん&ぶきっちょさんのためのお菓子一年生』(主婦の友生活シリーズ、主婦の友社)
↓応援クリックお願いします(^^)
宮崎市定氏が見る日本の清国留学生 ― 2009年02月12日
中公文庫に『中国文明の歴史』という中国史のシリーズがある。その中でも宮崎市定氏が執筆した『9 清帝国の繁栄』と『11
中国のめざめ』が好きで時々読み返している。宮崎市定氏はフランス留学経験があり(アラビア語)、またフランス・パリ大学、アメリカ・ハーバード大学、ドイツ・ハンブルク大学やルール大学でも教えたこともある人物で、欧米の東洋学についても造詣が深く、視野が広い。用語には旧いものも見受けられるが、その思考・論考は旧くなっていないと思う。
今回読み返したくなったのは『11 中国のめざめ』に日本に留学した学生の間で革命運動が盛り上がった理由として、こんなことが書いてあったのを思い出したからである。
「義和団事件から日露戦争直後まで、清国政府は多数の留学生を日本に送り、その多くは東京に滞在したが、その数が一時は数万人にも及んだという。ところがこういう新事態に対して、日本側では受け入れ態勢が少しもととのっていなかった。日本人は気が付かなかったが、宿舎も食物も、生活様式も、中国の上流社会の子弟には耐えがたい低水準であった。そのうえに中国人に中華意識があれば、日本人にも神国意識があった。しかも双方ともヨーロッパ諸国に対しては腹の中でコンプレックスを抱いていたから、なおさら事情が複雑である。日本人はロシアに対して戦勝の直後で鼻息が荒く、有色人種の中ではただ自分たちのみ、白人と対等になりえたような自信を獲得し、反面では自己を他の有色人種から区別するような態度をしばしばとった。これに対して中国人は、たとえ白人からはいささか軽蔑の態度を以て迎えられても、それはまったく異なる民族間の関係であるから不問に付するが、同じ有色人種の隣人、しかも従来は朝貢国視していた日本人から侮蔑の眼でみられることは、堪えることのできぬ屈辱と感ぜざるをえなかった。
そこで中国留学生のヨーロッパ、アメリカに滞在した者は多くその地の生活に満足し、良好な印象を得て安住したが、安住しすぎたためにそこでは革命運動はあまり流行しなかった。ところが日本在住の留学生は、心中に抱いている欲求不満が、革命の情熱となって爆発するのであった。革命運動にでも身を投ずるのでなければ、ほかに生き甲斐を感ずることができぬほど、日本の生活は不愉快なものであったらしい。」(p41-42)
以前読んだときは面白い見方があるものだと思っただけだった。でも今読み返してみれば、この時期の清国留学生、前述の京師大学堂の日本人教習・服部宇之吉や岩谷孫蔵が文部省に特別の配慮を依頼して送り込んだのではなかったか。日本人側は特別待遇したつもりだったにも関わらず、中国の上流社会の子弟にとっては日本の留学生活は「宿舎も食物も、生活様式も耐え難い低水準」であり、しかもそれに日本人は「気が付かなかった」というのである。なるほど、と思った。確かにこの時期京師大学堂に入れたのは貴族や官僚及び官僚予備軍といった、多くが広い邸宅で召使いに傅かれて育った上流階級の子弟である。明治の日本人が考えるところの学生宿舎ではとてもその要求に応えられるはずもあるまい。更にそれらの欲求不満が革命運動に結びつき、一方欧米の留学生は生活に満足して安住したから革命運動が流行しなかったという。欧米での生活経験はもとより、鋭い観察力と深い見識があってこそのさりげない文句の一つ一つに宮崎市定氏のすごさを感じる。
参考:宮崎市定『中国文明の歴史 11 中国のめざめ』(中公文庫、2000)
↓応援クリックお願いします(^^)

今回読み返したくなったのは『11 中国のめざめ』に日本に留学した学生の間で革命運動が盛り上がった理由として、こんなことが書いてあったのを思い出したからである。
「義和団事件から日露戦争直後まで、清国政府は多数の留学生を日本に送り、その多くは東京に滞在したが、その数が一時は数万人にも及んだという。ところがこういう新事態に対して、日本側では受け入れ態勢が少しもととのっていなかった。日本人は気が付かなかったが、宿舎も食物も、生活様式も、中国の上流社会の子弟には耐えがたい低水準であった。そのうえに中国人に中華意識があれば、日本人にも神国意識があった。しかも双方ともヨーロッパ諸国に対しては腹の中でコンプレックスを抱いていたから、なおさら事情が複雑である。日本人はロシアに対して戦勝の直後で鼻息が荒く、有色人種の中ではただ自分たちのみ、白人と対等になりえたような自信を獲得し、反面では自己を他の有色人種から区別するような態度をしばしばとった。これに対して中国人は、たとえ白人からはいささか軽蔑の態度を以て迎えられても、それはまったく異なる民族間の関係であるから不問に付するが、同じ有色人種の隣人、しかも従来は朝貢国視していた日本人から侮蔑の眼でみられることは、堪えることのできぬ屈辱と感ぜざるをえなかった。
そこで中国留学生のヨーロッパ、アメリカに滞在した者は多くその地の生活に満足し、良好な印象を得て安住したが、安住しすぎたためにそこでは革命運動はあまり流行しなかった。ところが日本在住の留学生は、心中に抱いている欲求不満が、革命の情熱となって爆発するのであった。革命運動にでも身を投ずるのでなければ、ほかに生き甲斐を感ずることができぬほど、日本の生活は不愉快なものであったらしい。」(p41-42)
以前読んだときは面白い見方があるものだと思っただけだった。でも今読み返してみれば、この時期の清国留学生、前述の京師大学堂の日本人教習・服部宇之吉や岩谷孫蔵が文部省に特別の配慮を依頼して送り込んだのではなかったか。日本人側は特別待遇したつもりだったにも関わらず、中国の上流社会の子弟にとっては日本の留学生活は「宿舎も食物も、生活様式も耐え難い低水準」であり、しかもそれに日本人は「気が付かなかった」というのである。なるほど、と思った。確かにこの時期京師大学堂に入れたのは貴族や官僚及び官僚予備軍といった、多くが広い邸宅で召使いに傅かれて育った上流階級の子弟である。明治の日本人が考えるところの学生宿舎ではとてもその要求に応えられるはずもあるまい。更にそれらの欲求不満が革命運動に結びつき、一方欧米の留学生は生活に満足して安住したから革命運動が流行しなかったという。欧米での生活経験はもとより、鋭い観察力と深い見識があってこそのさりげない文句の一つ一つに宮崎市定氏のすごさを感じる。
参考:宮崎市定『中国文明の歴史 11 中国のめざめ』(中公文庫、2000)
↓応援クリックお願いします(^^)
最近考えていること ― 2009年02月16日
ブログの書き込みがしばらく空いてしまった。最近ずっと19世紀から20世紀初めの頃の、欧米と中国、日本との関わりについて考えているのだけれど、どうも問題が大きすぎて、考えがまとまらないでいる(^^;)。ここ数日、『東洋学の系譜』『東洋学の系譜 欧米編』、宮崎市定『中国文明の歴史』9・11、陳舜臣『中国の歴史』、工藤美代子『ラフカディオ・ハーンの生涯』、阿部洋『中国の近代教育と明治日本』など…いろいろ並行して読みつつ、いろいろ考えを巡らせている。
これらの本を読んでいても気づくのは、ある同じ人物について書いていても、それぞれの立場で様々な見方があるということだ。それだけこの時期が思想的にも政治的にも複雑な要素を含んでいるわけで、客観的に捉え理解するのが思った以上に難しい。
プロテスタントの宣教師として最初に中国に入ったことで知られるロバート・モリソン。中国語を習得して、世界で最初に聖書の漢訳を行い、世界最初の『華英字典』を編纂し(本ブログ2008年8月10日参照)、1818年にはマラッカに英華学堂を設立し、「東の文化と西の文化の代表者が相互に理解し合うことまでも考えていた」(『東洋学の系譜 欧米編』)という彼でさえ、東インド会社の翻訳の仕事をしているし、母国の使節が北京に赴いたときの通訳もしている。聖書翻訳を続ける為にも、それらの仕事には経済的に助けられたようだ。 19世紀初旬、アヘン戦争以前の欧米にとって、中国との接点は開港地のみであった。ジェイスト派の宣教師は北京にいたが、それは例外として、欧米の宣教師が布教を目指して中国に上陸しても、布教が禁じられていたから商館等に商人に身をやつして住み込むしかなかった。ロバート・モリソンが、阿片を売る東インド会社と関わりを持ったのもそういう状況下であったから、ある程度は仕方がなかったのだろうとも思える。
でも、カール・ギャツラフあたりになると、どうも評価が難しい。陳舜臣『中国の歴史 7』(239頁)には「悪名高い帝国主義的な牧師ギャツラフ」とあり、「ギャツラフは白人優越の信仰をもち、東洋人を軽蔑していた人物で、牧師でありながら徹底した差別感を持っていました。アヘン戦争前、――英国のフリゲート艦一隻は、全清国海軍一千隻の兵船を撃破しうる。というたぶんに文学的な報告を送り、主戦論者を勇気づけました。」とある。でも一方で、カール・ギュツラフは、ドイツ人宣教師で日本人漂流民3名の協力を得て、世界初の和訳聖書『約翰福音之傳』を翻訳した人物であり、モリソンと同じロンドン伝道会(London Missionary Society)から派遣された宣教師であり、また「モリソン教育協会(Morrison Education Society)」の設立者の一人でもあるのだ。
19世紀の欧米人の中国への関心と関わり方についても、明治日本と中国・清朝政府との関わりについても、欧米から東洋学が日本に移植された経緯も、とても興味深い。ここを押さえておかないと、どうも先に進めない感じがしている。
↓応援クリックお願いします(^^)

これらの本を読んでいても気づくのは、ある同じ人物について書いていても、それぞれの立場で様々な見方があるということだ。それだけこの時期が思想的にも政治的にも複雑な要素を含んでいるわけで、客観的に捉え理解するのが思った以上に難しい。
プロテスタントの宣教師として最初に中国に入ったことで知られるロバート・モリソン。中国語を習得して、世界で最初に聖書の漢訳を行い、世界最初の『華英字典』を編纂し(本ブログ2008年8月10日参照)、1818年にはマラッカに英華学堂を設立し、「東の文化と西の文化の代表者が相互に理解し合うことまでも考えていた」(『東洋学の系譜 欧米編』)という彼でさえ、東インド会社の翻訳の仕事をしているし、母国の使節が北京に赴いたときの通訳もしている。聖書翻訳を続ける為にも、それらの仕事には経済的に助けられたようだ。 19世紀初旬、アヘン戦争以前の欧米にとって、中国との接点は開港地のみであった。ジェイスト派の宣教師は北京にいたが、それは例外として、欧米の宣教師が布教を目指して中国に上陸しても、布教が禁じられていたから商館等に商人に身をやつして住み込むしかなかった。ロバート・モリソンが、阿片を売る東インド会社と関わりを持ったのもそういう状況下であったから、ある程度は仕方がなかったのだろうとも思える。
でも、カール・ギャツラフあたりになると、どうも評価が難しい。陳舜臣『中国の歴史 7』(239頁)には「悪名高い帝国主義的な牧師ギャツラフ」とあり、「ギャツラフは白人優越の信仰をもち、東洋人を軽蔑していた人物で、牧師でありながら徹底した差別感を持っていました。アヘン戦争前、――英国のフリゲート艦一隻は、全清国海軍一千隻の兵船を撃破しうる。というたぶんに文学的な報告を送り、主戦論者を勇気づけました。」とある。でも一方で、カール・ギュツラフは、ドイツ人宣教師で日本人漂流民3名の協力を得て、世界初の和訳聖書『約翰福音之傳』を翻訳した人物であり、モリソンと同じロンドン伝道会(London Missionary Society)から派遣された宣教師であり、また「モリソン教育協会(Morrison Education Society)」の設立者の一人でもあるのだ。
19世紀の欧米人の中国への関心と関わり方についても、明治日本と中国・清朝政府との関わりについても、欧米から東洋学が日本に移植された経緯も、とても興味深い。ここを押さえておかないと、どうも先に進めない感じがしている。
↓応援クリックお願いします(^^)
まじょ子ブームの次は「なんでも魔女商会」ブーム ― 2009年02月17日
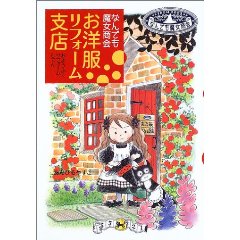
昨年夏以来、「まじょ子シリーズ」を図書館・図書室で借り続けた娘も、徐々に違う本にも興味を持つようになった。そのきっかけになったのが、あんびるやすこ「ルルとララ」シリーズで、最近夢中になって読んでいるのは、あんびるやすこ「なんでも魔女商会」シリーズである。
「なんでも魔女商会」シリーズの主人公は「おさいほう魔女」のシルクと人間の女の子ナナといういずれも可愛い女の子。「なんでも魔女商会」は人間以外なら誰でも知っている信頼ある魔法の老舗、そしてシルクは洋服のリフォーム支店を任されている腕の良いおさいほう魔女。このお店には本当に用事がある者だけが訪れることが出来る魔法がかかっている。そのお店に、転校したてで、お友達をほしがっていた人間の女の子・ナナが用もないのにやってくる。ナナが出会ったのは、鼻持ちならない少女のような外見の魔女・シルクと礼儀正しい召使い猫・コットン。このシルクが、友だちの人間の女の子・ナナと心を通わせるようになり、共に、様々なお客様(おばけだったり、妖精だったり、動物だったり…)の仕事を引き受け、洋服のリフォームを通じて、お客様に幸せを運び、そして友情を深めていくお話である。
ナナは人間の普通の女の子だから、読者の女の子も感情移入しやすい。それになんといっても、イラストが可愛く、ストーリーに魔法やお姫様や可愛いものがたくさん登場する。その上、お話に登場する服のデザインもオシャレで、素材も銀の蜘蛛の糸だったり、ネズミが編む春レースだったり、魔女の世界ならではの不思議なものばかりで、ロマンティックだ。おまけに可愛いチョーカーやコサージュ、ヘアバンドなど、簡単に作れるおしゃれなアクセサリーの紹介まである。この洗練されたオシャレさは、「バムとケロ」シリーズにも通じるような気もする。私の子ども時代はこんなにおしゃれな本はなかったと思うから、これは現代の日本文化を反映しているのかもしれない。
娘の読書は今のところ、ファンタジー専門である。「なんでも魔女商会」シリーズ、最新刊は12巻で、私と娘は図書館で10巻まで借りて読んだので、あと2冊。図書館ってありがたい。
読んでいる本:あんびるやすこ『なんでも魔女商会』シリーズ(岩崎書店、2003~)
あんびるやすこHP「ちいさなしっぽ協会」http://www.ambiru-yasuko.com/
「なんでも魔女商会」「ルルとララ」シリーズの作者・あんびるやすこさんのとても可愛いHPです。作品紹介の他、「忠告クッキー」(おみくじのような、フォーチュンクッキー)で遊べます。
↓応援クリックお願いします(^^)

「なんでも魔女商会」シリーズの主人公は「おさいほう魔女」のシルクと人間の女の子ナナといういずれも可愛い女の子。「なんでも魔女商会」は人間以外なら誰でも知っている信頼ある魔法の老舗、そしてシルクは洋服のリフォーム支店を任されている腕の良いおさいほう魔女。このお店には本当に用事がある者だけが訪れることが出来る魔法がかかっている。そのお店に、転校したてで、お友達をほしがっていた人間の女の子・ナナが用もないのにやってくる。ナナが出会ったのは、鼻持ちならない少女のような外見の魔女・シルクと礼儀正しい召使い猫・コットン。このシルクが、友だちの人間の女の子・ナナと心を通わせるようになり、共に、様々なお客様(おばけだったり、妖精だったり、動物だったり…)の仕事を引き受け、洋服のリフォームを通じて、お客様に幸せを運び、そして友情を深めていくお話である。
ナナは人間の普通の女の子だから、読者の女の子も感情移入しやすい。それになんといっても、イラストが可愛く、ストーリーに魔法やお姫様や可愛いものがたくさん登場する。その上、お話に登場する服のデザインもオシャレで、素材も銀の蜘蛛の糸だったり、ネズミが編む春レースだったり、魔女の世界ならではの不思議なものばかりで、ロマンティックだ。おまけに可愛いチョーカーやコサージュ、ヘアバンドなど、簡単に作れるおしゃれなアクセサリーの紹介まである。この洗練されたオシャレさは、「バムとケロ」シリーズにも通じるような気もする。私の子ども時代はこんなにおしゃれな本はなかったと思うから、これは現代の日本文化を反映しているのかもしれない。
娘の読書は今のところ、ファンタジー専門である。「なんでも魔女商会」シリーズ、最新刊は12巻で、私と娘は図書館で10巻まで借りて読んだので、あと2冊。図書館ってありがたい。
読んでいる本:あんびるやすこ『なんでも魔女商会』シリーズ(岩崎書店、2003~)
あんびるやすこHP「ちいさなしっぽ協会」http://www.ambiru-yasuko.com/
「なんでも魔女商会」「ルルとララ」シリーズの作者・あんびるやすこさんのとても可愛いHPです。作品紹介の他、「忠告クッキー」(おみくじのような、フォーチュンクッキー)で遊べます。
↓応援クリックお願いします(^^)
工藤美代子『ラフカディオ・ハーンの生涯』3部作を読む ― 2009年02月19日
先日母が送ってくれた、ノンフィクション作家・工藤美代子氏のラフカディオ・ハーン=小泉八雲の評伝三部作『夢の途上-ラフカディオ・ハーンの生涯(アメリカ編)』『聖霊の島-ラフカディオ・ハーンの生涯(ヨーロッパ編)』『神々の国-ラフカディオ・ハーンの生涯(日本編)』、ようやく読み終わった。この本を読んで、ラフカディオ・ハーン=小泉八雲が非常に個性的な人物であり、その人生が実に波瀾万丈だったことを知った。
一巻目のアメリカ編はラフカディオ・ハーンの青年期とその心の恋人と思われるエリザベス・ビスランドを追い求める旅である。単身の渡米、貧困の中での最初の結婚と破局、ジャーナリストとしての成功、彼の伝記を後に出版することとなるエリザベス・ビスランドとの出会いと関わり…著者の興味の中心はラフカディオと親しかった女性、エリザベス・ビスランドである。ビスランドはアメリカの女性ジャーナリストとしては先駆的な存在で、ラフカディオ・ハーンとも駆け出しの頃から面識があった。彼の死後は伝記と書簡集を出版し印税を全て遺族に贈って生活を援助している。ところが、ビスランドは、伝記と書簡集に収められたラフカディオ・ハーンのビスランド宛の手紙にある操作、編集を行った。つまり、ビスランドに対するハーンの恋愛感情ともとれる表現を全て消してしまった。それはなぜなのか、疑問に思った著者は、ビスランドゆかりの地を訪ねる旅に出る。各地で関係者の子孫や研究者を訪ね、図書館で史料を調査して、ビスランドの人間像や価値観、ラフカディオ・ハーンとの関わりを明らかにしていく。著者の大変な行動力と、史料を読み解く知性の高さには感服させられる。
二巻目のヨーロッパ編は、著者がギリシャとアイルランドへと赴き、ラフカディオ・ハーンの幼少期、少年期、彼の両親の出会いから破局までの経緯を追っていく。ただ、ラフカディオ・ハーンの両親について分からないことが多く、また母親が晩年を精神病院で過ごしたこともあって、著者の責任ではなく、手がかりがあまりにも少ないために、他の巻と比べ、精彩に欠いている。それでも、ラフカディオ・ハーンという人物の心の闇を知る為には、この巻はやはり必要だったのだろう。
三巻目の日本編はラフカディオ・ハーンが日本を訪れてから逝去するまでを追っている。そこからは彼の外国人教師としての生活、作家としての創作活動、妻・セツとの結婚と家庭生活が描かれている。日本人の妻・セツと築いた家庭を大切にするラフカディオ・ハーンは好ましかったし、明治日本における欧米人、欧米に紹介された日本像の片鱗を見ることが出来たのも良かった。そして最近の私が勉強している明治日本の教育界とも微妙ながら繋がったのが何よりありがたかった。明治の日本の帝国大学におけるお雇い外国人講師について、認識を深めることが出来た。
全編を通して、著者自らラフカディオ・ハーンゆかりの地を訪ね歩き、様々な史料を駆使しながら、ラフカディオ・ハーンの人生や人物像を解き明かしていくのは、その人生を追体験するようで、とても面白かった。また、著者がラフカディオ・ハーンの身内や友人、研究者の証言や著作については、客観的で公平な評価を与えようとしていたのには好感をもった。ただ、第三巻に描かれる、明治の日本に対する印象は、私が持っているイメージとは差異があり、違和感が残った。明治日本とはそんなに良き時代だったのか、という部分である。もちろん、私自身、小泉八雲については作品を少し読んだことがある程度で、ラフカディオ・ハーン=小泉八雲研究については全く無知な上、明治の日本についても専門家ではないから、正しい評価は出来ないのだが。 少なくとも、今後、小泉八雲の名前と作品を見たら、今までとは違う眼で、読むことになるだろう。
読んだ本:工藤美代子『夢の途上-ラフカディオ・ハーンの生涯(アメリカ編)』(ランダムハウス講談社、2008)
工藤美代子『聖霊の島-ラフカディオ・ハーンの生涯(ヨーロッパ編)』(ランダムハウス講談社、2008)
工藤美代子『神々の国-ラフカディオ・ハーンの生涯(日本編)』(ランダムハウス講談社、2008)
↓応援クリックお願いします(^^)

一巻目のアメリカ編はラフカディオ・ハーンの青年期とその心の恋人と思われるエリザベス・ビスランドを追い求める旅である。単身の渡米、貧困の中での最初の結婚と破局、ジャーナリストとしての成功、彼の伝記を後に出版することとなるエリザベス・ビスランドとの出会いと関わり…著者の興味の中心はラフカディオと親しかった女性、エリザベス・ビスランドである。ビスランドはアメリカの女性ジャーナリストとしては先駆的な存在で、ラフカディオ・ハーンとも駆け出しの頃から面識があった。彼の死後は伝記と書簡集を出版し印税を全て遺族に贈って生活を援助している。ところが、ビスランドは、伝記と書簡集に収められたラフカディオ・ハーンのビスランド宛の手紙にある操作、編集を行った。つまり、ビスランドに対するハーンの恋愛感情ともとれる表現を全て消してしまった。それはなぜなのか、疑問に思った著者は、ビスランドゆかりの地を訪ねる旅に出る。各地で関係者の子孫や研究者を訪ね、図書館で史料を調査して、ビスランドの人間像や価値観、ラフカディオ・ハーンとの関わりを明らかにしていく。著者の大変な行動力と、史料を読み解く知性の高さには感服させられる。
二巻目のヨーロッパ編は、著者がギリシャとアイルランドへと赴き、ラフカディオ・ハーンの幼少期、少年期、彼の両親の出会いから破局までの経緯を追っていく。ただ、ラフカディオ・ハーンの両親について分からないことが多く、また母親が晩年を精神病院で過ごしたこともあって、著者の責任ではなく、手がかりがあまりにも少ないために、他の巻と比べ、精彩に欠いている。それでも、ラフカディオ・ハーンという人物の心の闇を知る為には、この巻はやはり必要だったのだろう。
三巻目の日本編はラフカディオ・ハーンが日本を訪れてから逝去するまでを追っている。そこからは彼の外国人教師としての生活、作家としての創作活動、妻・セツとの結婚と家庭生活が描かれている。日本人の妻・セツと築いた家庭を大切にするラフカディオ・ハーンは好ましかったし、明治日本における欧米人、欧米に紹介された日本像の片鱗を見ることが出来たのも良かった。そして最近の私が勉強している明治日本の教育界とも微妙ながら繋がったのが何よりありがたかった。明治の日本の帝国大学におけるお雇い外国人講師について、認識を深めることが出来た。
全編を通して、著者自らラフカディオ・ハーンゆかりの地を訪ね歩き、様々な史料を駆使しながら、ラフカディオ・ハーンの人生や人物像を解き明かしていくのは、その人生を追体験するようで、とても面白かった。また、著者がラフカディオ・ハーンの身内や友人、研究者の証言や著作については、客観的で公平な評価を与えようとしていたのには好感をもった。ただ、第三巻に描かれる、明治の日本に対する印象は、私が持っているイメージとは差異があり、違和感が残った。明治日本とはそんなに良き時代だったのか、という部分である。もちろん、私自身、小泉八雲については作品を少し読んだことがある程度で、ラフカディオ・ハーン=小泉八雲研究については全く無知な上、明治の日本についても専門家ではないから、正しい評価は出来ないのだが。 少なくとも、今後、小泉八雲の名前と作品を見たら、今までとは違う眼で、読むことになるだろう。
読んだ本:工藤美代子『夢の途上-ラフカディオ・ハーンの生涯(アメリカ編)』(ランダムハウス講談社、2008)
工藤美代子『聖霊の島-ラフカディオ・ハーンの生涯(ヨーロッパ編)』(ランダムハウス講談社、2008)
工藤美代子『神々の国-ラフカディオ・ハーンの生涯(日本編)』(ランダムハウス講談社、2008)
↓応援クリックお願いします(^^)
最近のコメント