教会の女学校(改訂) ― 2008年06月01日
中国初の女学校は外国人、キリスト教会によって創立された。中国最初の女学校は1844年にイギリスの東方女子教育協進社(Society for Promoting Female Education in the East)のアルダーシー女史(Aldersey)が寧波に設立した女学校であったといわれている。
初期においては 教会の評判は非常に悪かった。地域住民とキリスト教徒の間で摩擦が生じることが多く、特に女性が教会堂に行くことは、宣教師のたぶらかし・誘惑と誤解された為である。布教当初は貧しい家の女の子を教会で養育することから始まったという。それ故、教育の内容も、聖書を読ませる為の識字教育、キリスト教の講義、職業教育の意味で家政科くらいのものであったらしいが、都市のミッション系の学校では、音楽、体育、外国語などの近代的な教育も徐々に行われるようになった。
教会の女学校は開港場を中心に増えていく。女性達の劣悪な家庭生活や不平等な社会は、欧米の市民社会を経験した宣教師からみると、纏足、女の赤ん坊の間引き、親の決める婚姻制度など、解決すべき問題を多く抱えていた。せっかく学校に入学させても、早婚の習慣により、ほとんどの学生は卒業を待たず中途退学してしまうことが多かった。そのため、ミッション系の学校では、女性の教育に早くから注目し、入学の条件として不纏足を掲げ、婚姻による退学を禁止するといった規定をもりこんだ。また、教会では早くから不纏足をよびかけ、教会関係者の連携によって、不纏足会や天足会が各地につくられた。教会とミッション系の学校は、弛まぬ努力により、中国女性解放の道を切り開いていったのである。
1877年にはプロテスタント系で121カ所、収容女子学生2101人という統計があり、1902年には四千余の女学生が教会の女学校に学んでいたという。
女子の医療教育も、優秀な女生徒を教会からアメリカの医科大学に留学させ、一方で女子医学院を設立させたことに始まる。1879年、広東にアメリカ長老教会が作った博済医院の医療班において、二名の神学院の女子学生が学んだことが、女子医学院設立の発端となった。
女子の高等教育は…1905年には華北協和女子大学、ついで福州に華南文理学院、南京に金陵女子大学などが作られ、嶺南大学は1905年から女子の受け入れを開始、1918年に男女共学になったが、これらの大学はいずれもミッション系である。
教会とミッション系の学校が、意図的に或いは無作為に、欧米の資産階級の女性解放理念を中国社会に導入したことで、遅れた中国の女子教育の先導役を務めることとなった。これが女子の高等教育と女子解放運動の先駆けとなったのである。
参考:中国女性史研究会編『中国女性の一〇〇年』、中華全国婦女連合会編著『中国女性運動史1919-1949』、小野和子『中国女性史』他
東シナ海を挟んだ日中文化交流 ― 2008年06月01日
しばらく前に、加藤徹「社会階層から見た日中文化交流 漢文派と唐話派」を読んだ。とても示唆的な内容だったので、読書日記として感想を残しておこうと思う。
加藤徹「社会階層から見た日中文化交流 漢文派と唐話派」東シナ海を挟んだ日本と中国の交流の特殊性が産んだ士人ルートと商人ルートの文化交流の構造を、史料によって読み解いたとても興味深い論文である。
まず、面白いのは日中の間を隔てる東シナ海の歴史的な役割の捉え方である。東シナ海の最高4ノットの強力な黒潮は、海域交流の壁となり、同時に対岸からの奇襲上陸の防御壁ともなっていたこと、近世東アジア諸国の「海禁」という世界史上珍しい管理貿易政策を可能にした論者は述べる。そしてこの文章の主軸でもある社会階層別の文化伝播のルートの存在を具体例で浮き彫りにしてくれるのである。それが、『明史』の、豊臣秀吉についての記述に「阿奇支」「明智」という二種類の明智光秀が登場するという論証である。論者によれば、前者は商人ルートによる「唐話(中国語会話)などによる情報、後者は士人ルートによる漢文の筆談や書籍など文字による情報であり、『明史』では二つの情報を合わせてねじれた事実認識をしてしまった、ということらしい。こういうことがあるのだ~、とただただ感心してしまった。他にもいろいろな興味深い例証があって、考えさせられるところが多かった。しかも士人ルート、商人ルート、移民ルートの三つのチャンネルは形を変えて今も生きているというから、すごい。
史料として残るのは、どうしても、士人ルートの情報が多いから、なかなか商人、移民ルートまでは目が届きにくいし、調査研究の方法も難しい。この論文は、とても示唆的で、今まで茫然と疑問に感じていた部分を解き明かしてくれたようで、とってもすっきりした。論者に感謝したい気分である。
参考:加藤徹「社会階層から見た日中文化交流 漢文派と唐話派」『大航海』No.66
イギリス人が創立した中国初のキリスト教女学校――東方女子教育協進社の試み ― 2008年06月03日
中国最初の女学校が1844年にイギリスの東方女子教育協進社(Society for Promoting Female Education in the East)のアルダーシー女史(Aldersey)が寧波に設立した女学校であったことは先に述べたとおりである。
学校創立の母体となった「東方女子教育協進社」、創立者「アルダーシー女史」、及び中国初の女学校について詳細を知るために先行研究を探したところ、佐藤尚子氏の論文「東方女子教育協進社による中国女子教育の開発」を見つけた。関心ある部分の覚え書きを残しておく。
東方女子教育協進社は1834年、アメリカ人在華宣教師・アビール(David Abeel)が中国女子教育の惨状に気がつき、女子教育必要性を訴えたことから、ロンドンで女侯爵を会長として組織された団体である。キリスト教伝道団体であるが、イギリスの国教会や宣教会とは関係がない、女子会員の年会費や寄附金によって支えられる団体であった。また東方女子教育協進社(Society for Promoting Female Education in the East)は中国のみを対象にした組織ではなく、「東方」(例えば1862年における出先機関はケープタウン、マドラス、ボンベイ、シンガポール、香港、モウリシャス、レバノン、カイロなど)の教育に広く関わろうとした組織であった。
東方女子教育協進社により、中国に最初に派遣されたアルダーシー女史(Mary Ann Aldersey、1797-1868)は裕福なロンドンの非国教徒の家庭の出身で、教派に属さない独立宣教師であった。アルダーシー女史は1816年から中国語の学習を開始、1937年にはバタビアで華僑女子のための学校を設立し、1844年に中国・寧波の中心部に広い家を借りて中国初の寄宿制女学校を設立した。
中国・寧波における学校経営は困難を極めたようである。まず生徒がなかなか集まらなかった。開校から1年後には18名、8年後にも40名が在籍しただけであった。一つには外国人とキリスト教に対する偏見が関係していた。「子供の目玉を取って薬にする」「悪魔であり、子供に悪魔の心を植え付ける」と言われていた。そして何よりも、中国の伝統的慣習と思想が最大の障害であった。
教育内容は共通の学科(これは何を指しているか分からない。聖書を読む為の識字教育と宗教教育であろうと思われる)、裁縫と刺繍であり、実際の女子の生活に合わせる努力を行ったらしい。音楽、体育などの近代的な教育カリキュラムはアルダーシー女史の学校にはなく、全体的に程度の低い教育内容だったと見られる。
それでも、この学校の設立の意義は大きかった。東方女子教育協進社の学校設立以降、開港地にはキリスト教女学校が次々と開設され、それは中国人の女子教育への認識の変化にも繋がっていった。教会の女学校が、中国における女性解放の種をまいた、ことは確かであるようだ。
参考:佐藤尚子「東方女子教育協進社による中国女子教育の開発」http://www.sap.hokkyodai.ac.jp/otu/reports.html
フィンランドの学力を世界一にした教育相オッリペッカ・ヘイノネン ― 2008年06月04日
PISAでフィンランドが学力世界一を二回連続で達成したことで、日本でも「フィンランド・メソッド」が注目され、解説書や教科書の翻訳版が出版されている。それらに目を通した感想については以前書いた。しかし、その時点では、教育方法、教科書の素晴らしい部分は感じつつも、解説や本文から透けて見えてくるフィンランドという国について未知の部分が多すぎた。
そこで読んでみたのが、『オッリペッカ・ヘイノネン「学力世界一」がもたらすもの』(NHK出版)である。これはフィンランドの教育改革を主導したオッリペッカ・ヘイノネン元教育相を教育学者・佐藤学氏がインタビューした記録であり、佐藤氏自身がフィンランドを訪れて各地の学校を視察した結果を踏まえたフィンランド教育の分析を分かりやすく披露した本でもある。
佐藤学氏の解説を読んで分かったことだが…フィンランドの学校は日本や中国とはずいぶん違うのである。フィンランドは人口520万であるが、国土面積は日本とあまり変わらない。人口密度は日本と比べて相当低い。学校は子供の居住地から半径5キロ以内に建設することが法律で決まっており、3キロ以内はスクールバスが、3~5キロ以内の子供はタクシー(公費)で通学している。小学校は平均して70名程度、中学校と高校は150名程度だそうである。都市郊外、田舎の小学校では、生徒60名ほど、教師は校長を含めて3-4名、給食の職員1名、中学校と高校では生徒150名程度、教師が10-12名、給食の職員が2名に、スクールカウンセラーが1名というのが一般的である。従って学級規模も小さく、小学校の一学級は20名程度、中学校と高校の一学級は16名程度、学級の規模が小さい為、複数学年が一クラスになる複式学級が多いという。
国の教育への保護も厚い。たとえば、フィンランドの学校は…教科書の他、鉛筆、消しゴム等の学用品は全て配られ、学費はもちろん、給食費も無料である。私立も公立も、国内のどこに住んでいても全く変わらない水準の教育を受けられるよう配慮されている。PISAでは、フィンランドは男女共に世界一の水準の学力であり、男子生徒が優位とされる科学リテラシーと数学リテラシーにおいても、女子生徒が男子生徒と同等の成績を達成していたという。また、学力平均が高く、学力格差が少なく、そして成績下位者が驚くほど少ないというのが大きな特徴であったらしい。
また、教科書に検定制はなく、国家は教育目標の大まかなところを決めているくらいで、教育内容については地方自治体や学校の自由裁量に任されている。教師の質も高い。教師は、幼児教育は学部レベル、小中学校教育は修士レベルの学歴が必要である。ついでながら教師は最も人気のある職業で、最も優秀な学生がなる職業だという。
実はフィンランドも1990年代初め、失業率20%を越える不況に苦しんでいた。この危機に際し、フィンランドは教育に関わる公務員を増やし、教育に莫大な予算を投入、即ち国の未来を背負う教育に投資し、現場の教師達とも意思疎通を図りながら改革をやり遂げたのである。結果IT産業の成長で景気は回復、経済成長と教育改革の両方を成功させた。当時の教育相オッリペッカ・ヘイノネン氏の洞察力と改革方法の素晴らしさは、成功の大きな要素であったと思う。もっとも、この成功には、フィンランドの国民性、文化、社会構造など、複合的な要素が背景にあり、日本ではそのまま通用はしないだろう。それでも、大いに参考になるはずだ。経済危機にあって、むしろ教育に投資して人材を育成することで新しい産業を興し、或いは産業を活性化させる、という思考法と方向性は日本でも十分通用するし、また国民ものぞんでいるのではないかと思う。
ここまで考えて気がついたのは、中国の近年における「素質教育」の流れ(重点学校や重点クラスを廃止し、教育の機会の平等を図り、発想力や創造力などの資質向上の教育を推進する)は、教育の質と平等の両方を実現したフィンランド・メソッドに関係があるかもしれない。PISA及びフィンランド教育に対する中国における反応を確認してみよう。
最後に佐藤氏とのインタビューでオッリペッカ・ヘイノネン氏が引用した格言を紹介して終わろう。
It takes a village to raise a child ひとりの子供を育てるには一つの村が必要(アフリカの格言。社会全体で教育制度を考えなくては、という意味合いから) Non scholae sed vitae discimus. 学校のためでなく人生の為に学ぶ(ラテン語の格言)
参考:『オッリペッカ・ヘイノネン「学力世界一」がもたらすもの』(NHK出版)
紫禁城に少年宮が造られたわけ ― 2008年06月10日
中国の「少年宮」をご存知だろうか。5歳から16歳までの少年少女が通う、校外活動施設のことである。芸術活動、スポーツ活動、科学技術、文化活動他があり、様々な分野の人材を多く輩出してきた。特に宋慶齢が創設した上海「中国福利会少年宮」と紫禁城にある北京「北京市少年宮」は有名である。
中でも、北京市少年宮は紫禁城の「寿皇殿」(皇帝の山登りや花見の為に建てられた宮殿)にある。天安門前を通るたびに、大きな看板が目に入り、なぜここに「少年宮」があるのか、不思議に思ったものだ。最近になって建設の経緯を知った。
話は1952年に遡る。この年、北京の北海北岸の「闡福寺」に「少年之家」が造られ、以来、外国の訪中団が中国の少年の校外活動に興味を持って度々訪れるようになった。この少年の家は狭く、設備も粗末であったところから、中国の少年少女の校外活動を紹介する場として建設地に選ばれたのが、紫禁城の「寿皇殿」だったのである。紫禁城は民国時代からすでに一般の参観に開放されていた。それでも、少年少女の校外活動の拠点をわざわざ元・皇宮内に建設したのは、新国家・中華人民共和国の面子を保つ為の措置、いわば政治判断であったと思われる。
北京市少年宮は当時の北京市長・彭真等の指導下で建設がすすめられ、1956年1月1日にオープンした。式典当日には、少年庁に500名の赤いネッカチーフ(紅領巾)をつけた少年先鋒隊隊員が一堂に会し、その前で副市長はこう宣言したという。「北京市の少年、児童に、私はここで宣言します。今日私は市の人民政府を代表し、この美しい少年宮を皆さんに贈ります。今日から、きみ達はこの宮殿の主人です。君たちがよく学び、健康に成長し、我々の偉大な祖国を建設する準備をしてくれることをのぞんでいます」
この日から、北京少年宮はいわば中国の少年少女の校外活動の場の象徴的存在となり、党のリーダーを始め、外国の元首、訪中団などが多く訪れた。創立50周年の2006年には様々な記念行事が行われた模様である。なお、近年になって文化財の保存の立場から、この場所に少年宮があることは好ましくないということになり、引っ越しが決まって調整が進んでいるらしい。
『女子國文讀本』にみる清朝末期の思想教育 ― 2008年06月10日
1905年(光緒31年)上海・商務印書館から出された『女子國文讀本』を見ると、康有為や梁啓超等の不纏足と婦女解放の論理は、変法運動失敗後も、中国における女性教育の基礎的な思想として生き続けたことが良く分かる。第一課から第四課までを見てみよう。
始めに第一課から第四課で女性の問題を述べる。第一課で「男性が苦しくないのは、学問をするからである。女性の苦しみは、纏足をするからである。」として学問の大切さと同時に纏足の弊害を説き、第二、三課では女性が学問することの意義と学校教育の良さを述べ、第四課では再び「纏足の法は妓女の法である」として纏足の害を訴える。
一方、国民の自覚を持たせる教育も行われている。第五課から第八課である。まず、第五課で「人が多いのは村、更に多いのは鎮、更に多いのが県、更に多いのが府、そして省である。各省を一つにしたものが国であり、名を[中国]という。」として国の構成を述べ、続いて第六課で「浙江は中国の一省であり、湖州は浙江の一府であり、烏程は湖州の一県である。私が住む南潯鎮は烏程に属している。」と具体的に地名で説明し、第七課では「中国は私の国である。中国の富強は私の栄えである。中国の貧弱は私の恥である。私は女子であるが国を守る責任があるのである。」と教える。その後念押しするように、第八課「南潯鎮の人は烏程県の人であり、烏程県の人は湖州府の人であり,湖州府の人は浙江省の人であり,浙江省の人は中国人である。ゆえに私は中国人である。」と第六課とは反対の順序で述べて、女児に中国人としての自覚と責任をうながすのである。
ところで、第5-8課と同じような発想で中国人の自覚をうながす文章を、台湾の戦後初期の教科書『小学国語課本』で見たことがある。この時に私が見たものは奥付がなく、出版年度も出版地も不明であったが、後に資料集で同じ内容のものを見つけ、戦後初期の教科書であることが確認できた。この教科書の第一冊、第一課のタイトルは「台湾人」、課文は「私は台湾人です。あなたも台湾人です。彼も台湾人だ。我々はみな台湾人です」であり、続く第二課は「中国人」、内容は「我々の祖先は福建人、広東人です。福建人、広東人、台湾人、みな中国人です」となっている。出てくる地名は違うけれども、発想はよく似ている。 女性に中国人としての自覚を持たせる教育と、台湾が中国に「光復」したとき、台湾人に中国人としての自覚を持たせる為の教育に共通点があるというのは、興味深い発見だった。
『ぐりとぐら』のひみつ!? ― 2008年06月12日
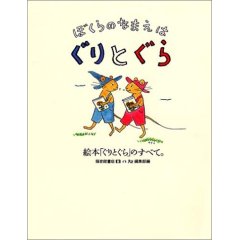
私自身が幼い頃大好きで、娘にも読み聞かせをした思い入れの深い絵本『ぐりとぐら』。『ぼくらのなまえはぐりとぐら-絵本「ぐりとぐらのすべて」』(福音館書店、2001年出版)を図書館で見つけた。ふと手にとってページをめくると、作者姉妹の対談が載っているではないか。「ぐりとぐら」名前の由来は?なんていうのもある。面白そうだ。
『ぐりとぐら』の名前の由来はフランスのPierre Probst作の絵本『プッフとノワロ(Pouf et Noiraud )』から。若い頃フランス語を習っていた姉妹は、フランス語の先生から借りた絵本を訳し、中川さんが紙芝居にして保育園の子ども達に聞かせていた。「プッフ」は白い猫、「ノワロ」は黒い猫、この猫が、ゴーグルをしてオートバイにのり(キャンプ道具を全部のせて)、マフラーをたなびかせてキャンプに行く、当時の日本にはない、とってもいかした設定に子供達、特に男の子は夢中になったという。
中川さんによれば「…そしていい気持ちでキャンプファイヤーをしてハーモニカを吹いて楽しんでいるところへ、ノネズミの一団がやってくるんです。そうすると、なんとその猫たちはネズミが大嫌いという変な猫で(笑)、慌てて、そばの木に登る。その間にノネズミたちがどんちゃん騒ぎをするのね。その歌があるんです。[なんてここは素敵なんだろう]って。[ぐりっぐるぐら、ぐりっぐるぐら]ってリフレインが付くの。そうすると子どもが待っていましたと、一緒になって[ぐりっぐるぐら、ぐりっぐるぐら]って言うんですよ。そこからもらったの。[ぐり]と[ぐら]」というわけらしい。
ちなみに「[ぐりっぐるぐら、ぐりっぐるぐら]は[ガリガリガリ]なのだそう。」(「ぐりとぐらのえんそくがおわって」)ネズミのかけ声、それともひっかく音?まあ、それはともかく、この本のおかげで、ぐりぐらの名前の謎もとけたし、他にもぐりとぐらが男の一卵性双生児だということも判明した。5人兄弟の2番目だった中川さん、双子にあこがれていたそうだ。
他にも、本作りのいろいろなエピソードを作者が語っていたり、外国語に訳されたぐりとぐらを紹介(CD付で英語と中国語と韓国語については朗読も)していたり、読者がぐりぐらの歌につけた曲(CDにも入っています)が紹介されていたり、著名人や研究者による評が載っていたり、ぐりとぐらの洋服や折り紙の折り方、カボチャのスフレケーキのレシピが紹介されていたり…、ぐりとぐらを何倍も楽しめるとっても素敵な本である。とびっきりのファンはとっくに知っていたに違いないが、私にとってはワクワクがいっぱいの本に出会えてちょっと幸せをお裾分けしてもらったような気持ちだった。
読んだ本:『ぼくらのなまえはぐりとぐら-絵本「ぐりとぐらのすべて」』(福音館書店、2001年出版)
ピーターラビット ― 2008年06月13日
ピーター・ラビットの生みの親ミス・ポターのこと ― 2008年06月13日

『“ピーターラビット”の生みの親ミス・ポターの夢をあきらめない人生』を読んだ。この本からは、作品についてのささやかだけれど興味深い事実を、沢山知ることが出来る。例えば…1901年に発売された私家版を買ってくれた人にコナン・ドイル(作家、推理小説シャーロック・ホームズシリーズの作者)がいたこと、ビアトリクスが描いた場所や家や動物にモデルがあること、ピーター・ラビットやベンジャミンのモデルはビアトリクスがロンドンの自宅で飼っていたうさぎだったこと、あひるの卵をメンドリに孵させる(『あひるのジマイマのおはなし』)のは湖水地方の農家でよく行われているらしいこと、などなど…。
もっとも、本書は作品そのものではなく、作者ヘレン・ビアトリクス・ポターの生き方をたどった内容である。ピーター・ラビットは世界中の子ども達に愛されているけれども、作者についてはあまり知られていなかった。映画「ミス・ポター」に描かれるビアトリクスも彼女のごく一面である。実は作者本人がプライベートを非常に大切にしており、日記も彼女が考案した暗号で書かれていたというから、知られないことこそが作者の望みだったに違いない。
本書によれば、作者ヘレン・ビアトリクス・ポターは1866年に中産階級の家庭に生まれた。イギリスでアッパー・ミドル・クラスといえば、なかなかの富豪である。実際、ポター家は、お屋敷に住んで大勢の使用人を使い、日々パーティを開き、子ども達には乳母と様々な学科の家庭教師を雇い、避暑のために3ヶ月別荘に暮らしても、財産だけで優雅に暮らしていける、という経済状態だったようである。父親は法廷弁護士の資格を持っていたがほとんど働くことなく、紳士クラブに出入りして社交と趣味の写真を楽しんでいたらしい。一方、当時のアッパー・ミドル・クラスの子ども達が受ける教育といえば、男の子は11歳になるとパブリックスクール(寄宿舎学校)の寮に入って家族と切り離された生活を送り、女の子はずっと自分に与えられた部屋にいて専ら通ってくる家庭教師から勉強を習っていた。ビアトリクスも当時の慣習の例外ではなく、年齢に応じて読み書き、算数、ドイツ語、フランス語、歴史、地理、文法、両親の理解を得て水彩画、ドローイングを通いの家庭教師から習い、家どころか自分の部屋からさえ出ないような、文字通りの深窓の令嬢であった。
そのビアトリクスが、絵と創作の才能とビジネスの才覚によって成功をおさめ、愛する婚約者との死別を乗り越え、恋愛結婚を保守的で頑固な親に認めさせる過程はとても見応えがある。豊かな暮らしが約束される階級に属しながら、階級を乗り越えて、自立の道を模索し続けたビアトリクス、彼女が人生をきりひらく原動力となったものは、いったい何だったのだろう。結婚後は農業に目覚め、愛する湖水地方の環境保護のために様々な活動を行い、死後はナショナルトラストに多くの土地や建物を寄贈している。
私が特に興味を持ったのは、彼女が生きた時代とその活動の内容である。ビアトリクスが生まれた19世紀半ばはイギリスが産業革命で黄金期を迎え、世界の工場と言われていた絶頂の時代であるとともに、婦人参政権を求めて過激な活動を行ったことで有名なエメリン・パンクハーストなどが活躍した時期でもある。ビアトリクス・ポターが認められていった背景には、イギリスの上・中産階級の出身の女性が、自立を求めて果敢に社会へ出ていき、社会的地位を確立していく時代の雰囲気というものがあったような気がする。
読んだ本:伝農浩子『“ピーターラビット”の生みの親ミス・ポターの夢をあきらめない人生』(徳間書店、2007年)
『受けてみたフィンランドの教育』読んでみました ― 2008年06月15日

最近関心を持っているフィンランドの教育、もっと深く知りたくなって、『受けてみたフィンランドの教育』を読んだ。OECDのPISA(生徒の学習到達度調査)で世界トップクラスと認められたフィンランドの教育、その内側を知るにはもってこいの本であった。
本書はフィンランドの高校に一年間高校生留学した実川真由さんの体験記と翻訳家(英語)でライターでもある母親・実川元子さんの解説で構成されている。
実川真由さんはAFS(高校生の国際教育交流を主催している組織)の留学生として、ホームステイしながら、フィンランドの首都ヘルシンキ市内にあるヘルトニエミ中高一貫総合校で一年間を過ごした。真由さんが気付いたフィンランドの教育の特徴はいろいろある。まず、教育は基本的に無料であること(給食や寮費も)、小中学校でも留年する子供が多いこと(多くのフィンランド人は理解しないまま学年だけ上がることよりはきちんと理解できるまで勉強してゆっくり学年が上がっていく方がいいと考えているから、親も教師も留年したからダメな子供というレッテルを貼ることはなく、「この子は読むのが苦手だから」と考えるだけ)、試験はどの学科もほとんどが記述式であること、校則がないこと、塾がないこと(医学部を受験する人向けのサマースクールなどはある)、高校を卒業してもそのまま大学へいく人は少数であること、試験勉強は「暗記」ではなく「読む」ことであったこと(数学を含む多くの学科のテストは記述式であり、知識及び物の考え方が厳しく問われるため、試験前には本を読んで知識を蓄えるしかない)、授業でも物事を論理的に考えることと相手に分かるように説明することを随時求められること、等々。教育を受けやすい国だけれど、教育の場で求められることは簡単ではない。それでも私的にはフィンランドのような勉強の方が断然好きだ。日本でもこういう学校を選べたらどんなにいいだろう。
本書や元教育相のオッリペッカ・ヘイノネン氏の本を読む中で分かってきたのは…フィンランドの教育重視の政策はいわば小国フィンランドの生き残り策であるということだ。フィンランドは資源の少ないため、国民こそが財産であり、その国民が少ないから、国民全体の資質を底上げする必要があるのである。
日本とフィンランドでは教育の背景となっている歴史も社会も様々に異なるが、教育政策面でも国民の意識面でも、フィンランドの方が進んでいる部分がたくさんあることは確かであるようだ。また、思考力を鍛えることは、現代の国際情勢に必要な人材育成という観点からも、正しい方向のように思われる。
ちなみに、著者の実川真由さん、最初は日本の高校との様々な違いに戸惑い、又シャイなフィンランドの国民性もあって友人作りにも苦労したが、本人の努力と何事も学ぼうとする積極性に加え、ホストファミリーや学校の教師の支えもあって、徐々に馴染んでいき、最後には英語のエッセイも飛躍的に進歩し、習得が困難と言われるフィンランド語でプレゼンテーションできるようにもなり、40人もの友人がお別れパーティに集まって別れを惜しんでくれたというから、留学生活はとても有意義なものだったようだ。
体験記を読んでいる内に、教育のことはおいても、フィンランドが魅力的な人がたくさん住んでいそうでワクワクした。いつかフィンランドに滞在してみたくなった。
読んだ本:実川真由・実川元子『受けてみたフィンランドの教育』
参考:AFS日本協会HP: http://www.afs.or.jp/jpn_ja/home
最近のコメント