司馬遼太郎と戦前教育――松本健一『司馬遼太郎を読む』を読む ― 2009年11月04日

松本健一『司馬遼太郎を読む』を読みはじめて、いきなり興味深い話題に行き当たった。蒙古襲来から日本を救った「神風」は昭和9年2月改訂の『尋常小学国史』で「大風」から「神風」となり、天皇は「現人神」扱いされるようになったという。小学国史は小学校5年生からの歴史教科書、司馬遼太郎は昭和9年に小学校五年生だから、「神がかり」の時代に入っていく教科書の第一期生だったということになる。松本氏はまた、『菜の花の沖』の主人公・高田屋嘉平について「司馬さんはどうしてこのような人物を書いたのだろう?」と調べている。その結果、松本氏が見つけたのは、昭和9年頃の修身の教科書だった。「司馬さんが小学校の高学年のころ、修身の教科書の中に、[勇気]について書かれた物語りがあった。これが高田屋嘉平の物語りなのです。」と述べている。
司馬遼太郎といえば、以前『世に棲む日日』の「文庫版あとがき」で「私は日本の満州侵略のころはまだ飴玉をしゃぶる年頃だったが、そのころすでに松陰という名前を学校できかされた。松陰は明治国家をつくった長州系の大官たちが伊藤博文は意識的に無関心だったが――国家思想の思想的装飾としてかれの名を使って以来、ひどく荘厳で重苦しい存在になった。私は学校ぎらいの子供だったから松陰という名が毛虫のようなイメージできらいだった」と語るなど、戦前教育に対しては、嫌悪感のようなものを持っていたという印象が私にはあった。でも、強い嫌悪感は、一方で、強い影響を受けた証でもあるのだろう。この世代の方に共通の心の傷のようなものがあるような気もする。
ところで、松本氏の論じる司馬遼太郎はなかなか厳しいのだけれど、『司馬遼太郎を読む』は、楽しく読める本である。松本氏の鋭い論評のなかの心が通った温かい部分を取り出したような本のような気がする。松本氏の司馬遼太郎との交流や見方、そのあたりも垣間見えて、楽しい。
読んだ本:松本健一『司馬遼太郎を読む』(新潮文庫、2009)
↓応援クリックお願いします(^^)
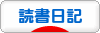
司馬遼太郎といえば、以前『世に棲む日日』の「文庫版あとがき」で「私は日本の満州侵略のころはまだ飴玉をしゃぶる年頃だったが、そのころすでに松陰という名前を学校できかされた。松陰は明治国家をつくった長州系の大官たちが伊藤博文は意識的に無関心だったが――国家思想の思想的装飾としてかれの名を使って以来、ひどく荘厳で重苦しい存在になった。私は学校ぎらいの子供だったから松陰という名が毛虫のようなイメージできらいだった」と語るなど、戦前教育に対しては、嫌悪感のようなものを持っていたという印象が私にはあった。でも、強い嫌悪感は、一方で、強い影響を受けた証でもあるのだろう。この世代の方に共通の心の傷のようなものがあるような気もする。
ところで、松本氏の論じる司馬遼太郎はなかなか厳しいのだけれど、『司馬遼太郎を読む』は、楽しく読める本である。松本氏の鋭い論評のなかの心が通った温かい部分を取り出したような本のような気がする。松本氏の司馬遼太郎との交流や見方、そのあたりも垣間見えて、楽しい。
読んだ本:松本健一『司馬遼太郎を読む』(新潮文庫、2009)
↓応援クリックお願いします(^^)
最近のコメント