中国の天文史と西欧の接点 ― 2009年08月05日
今年は世界天文年、ガリレオ・ガリレイが望遠鏡で月を観察してから、400年である。中国の天文学の歴史を調べていて、興味深いことを見つけた。ガリレオと知り合いで、ケプラーとも親交があったジョアン・テレンス(Jean Terrenz、中国名:鄧玉函)という医学者が、イエズス会の宣教師として中国へ渡り、西洋天文学のエンサイクロペディアである『崇禎暦書』の編纂に携わっていたのである。
中国にいる間も、ドイツ他の天文学者と文通を続けており、それもあって、明末に編纂されたこの暦書はドイツの暦算学の大きな影響を受けているという。ヨーロッパの天文学が飛躍的に発展したこの時期に、ガリレオを直接知る人物が、極東の中国北京で新しい暦書を編纂していたのだ。天文学に造詣が深く、武器などにも明るく、中国語をマスターする意欲もある…といった人物は、ヨーロッパ広しといえども、非常に限られていたはずだ。それほどの人材を次々に中国に送り込んだイエズス会の本気が感じられる。
1600年代といえば、日本は江戸時代に入ったばかり、当の中国も明から清へ…国が大混乱している時期である。その混乱の中に多くの宣教師が中国で過ごしながら、宣教の機会を待っていたというのもすごいことのような気がする。
↓応援クリックお願いします(^^)
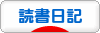
中国にいる間も、ドイツ他の天文学者と文通を続けており、それもあって、明末に編纂されたこの暦書はドイツの暦算学の大きな影響を受けているという。ヨーロッパの天文学が飛躍的に発展したこの時期に、ガリレオを直接知る人物が、極東の中国北京で新しい暦書を編纂していたのだ。天文学に造詣が深く、武器などにも明るく、中国語をマスターする意欲もある…といった人物は、ヨーロッパ広しといえども、非常に限られていたはずだ。それほどの人材を次々に中国に送り込んだイエズス会の本気が感じられる。
1600年代といえば、日本は江戸時代に入ったばかり、当の中国も明から清へ…国が大混乱している時期である。その混乱の中に多くの宣教師が中国で過ごしながら、宣教の機会を待っていたというのもすごいことのような気がする。
↓応援クリックお願いします(^^)
最近のコメント