司馬遼太郎『世に棲む日々』3,4を読む ― 2009年07月17日
司馬遼太郎『世に棲む日々』を読み終わった。1,2巻の感想はすでに書いた。3,4巻は吉田松陰の死を受け、また上海での見聞を経て、革命への道をひた走り、革命成功前夜に死を迎えるまでが描かれている。この部分を読んでやっと、吉田松陰の部分はいわばプロローグであり、司馬さんが書きたかったのは本人も言っているように高杉晋作であったことがよく分かった。
高杉晋作の人生は非常にドラマチックだ。綱渡りのような人生に、どきどきしながらページをめくった。私が注目したのは、彼の人生を大きく変えたきっかけが、上海を訪れたことであったことである。アヘン戦争で敗北し、香港を租借、上海等5港を開港した清末の中国を彼は見ているのだ。高杉晋作には上海がどのように映り、どのような感想をもったのか、とても興味がある。それというのも、高杉晋作という一個人の上海における見聞が、後にパークスとの停戦交渉における彦島租借要求を断固拒否したことにつながっており、また下関開港の提唱につながったことを踏まえると、このときの訪中の意義はとてつもなく大きいからである。
彦島が租借されていたら、彦島と下関は、香港島、九龍半島の如くになっていたに違いない。紛うことなく、上海行きを境に、高杉晋作の目には世界が映っていたのだ。もっとも同じ船で正使として赴いたはずの幕府の役人は無能揃いであり、諸藩が派遣したのは藩きって秀才でその多くが維新において活躍した人材に育ったことを司馬さんは指摘する。高杉晋作をこの時期に上海に送ることが出来たことは、日本にとっては大いなる幸いだったといっていいだろう。
司馬さんは、ある人物を描くとき、大量の史料を読み込み駆使して、歴史に埋もれた細事の一つ一つから人間像や当時の人間関係等を再構築し、そこから事跡を分析、行動の有り様を推理し、これを実に生き生きと描く。この手法が実に鮮やかなので、司馬さんの描く人物像…吉田松陰、高杉晋作、伊藤博文等…をそのまま鵜呑みにしたくなる。松本健一『司馬遼太郎』で論じられているように、司馬さんの描く人物像はあくまでも司馬さんが描いて見せた小説の世界に息づくものであって、必ずしも歴史の事実ではないことは分かっていても、司馬さんの語りの巧みさに思わず酔わずにはいられない。
読んだ本:司馬遼太郎『世に棲む日々』3,4(文春文庫)
↓応援クリックお願いします(^^)
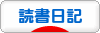
高杉晋作の人生は非常にドラマチックだ。綱渡りのような人生に、どきどきしながらページをめくった。私が注目したのは、彼の人生を大きく変えたきっかけが、上海を訪れたことであったことである。アヘン戦争で敗北し、香港を租借、上海等5港を開港した清末の中国を彼は見ているのだ。高杉晋作には上海がどのように映り、どのような感想をもったのか、とても興味がある。それというのも、高杉晋作という一個人の上海における見聞が、後にパークスとの停戦交渉における彦島租借要求を断固拒否したことにつながっており、また下関開港の提唱につながったことを踏まえると、このときの訪中の意義はとてつもなく大きいからである。
彦島が租借されていたら、彦島と下関は、香港島、九龍半島の如くになっていたに違いない。紛うことなく、上海行きを境に、高杉晋作の目には世界が映っていたのだ。もっとも同じ船で正使として赴いたはずの幕府の役人は無能揃いであり、諸藩が派遣したのは藩きって秀才でその多くが維新において活躍した人材に育ったことを司馬さんは指摘する。高杉晋作をこの時期に上海に送ることが出来たことは、日本にとっては大いなる幸いだったといっていいだろう。
司馬さんは、ある人物を描くとき、大量の史料を読み込み駆使して、歴史に埋もれた細事の一つ一つから人間像や当時の人間関係等を再構築し、そこから事跡を分析、行動の有り様を推理し、これを実に生き生きと描く。この手法が実に鮮やかなので、司馬さんの描く人物像…吉田松陰、高杉晋作、伊藤博文等…をそのまま鵜呑みにしたくなる。松本健一『司馬遼太郎』で論じられているように、司馬さんの描く人物像はあくまでも司馬さんが描いて見せた小説の世界に息づくものであって、必ずしも歴史の事実ではないことは分かっていても、司馬さんの語りの巧みさに思わず酔わずにはいられない。
読んだ本:司馬遼太郎『世に棲む日々』3,4(文春文庫)
↓応援クリックお願いします(^^)
最近のコメント